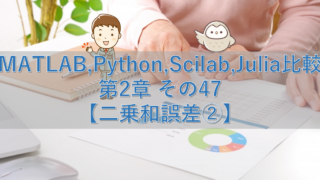 数値計算
数値計算 MATLAB,Python,Scilab,Julia比較 第2章 その47【二乗和誤差②】
多変量について説明。
いっぱい変数あるってこと。
二乗和誤差を多変量で表現。
ベクトル、行列で表現するってこと。
一般化した後に具体化して確認。
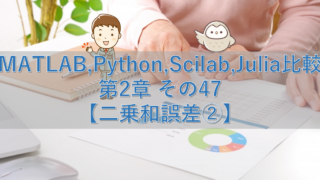 数値計算
数値計算 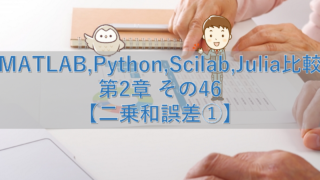 数値計算
数値計算  数値計算
数値計算 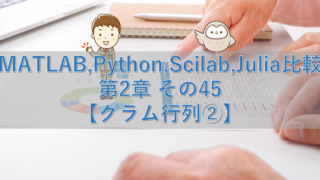 数値計算
数値計算 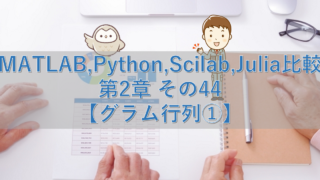 数値計算
数値計算 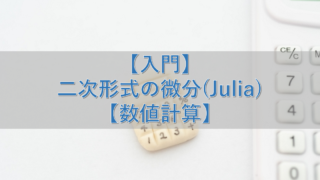 数値計算
数値計算 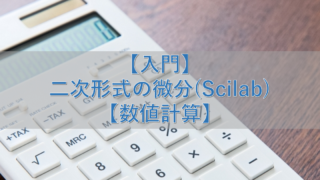 数値計算
数値計算 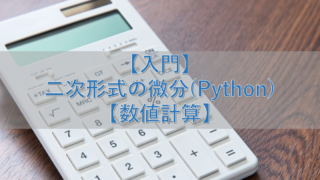 数値計算
数値計算 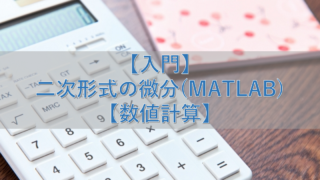 数値計算
数値計算 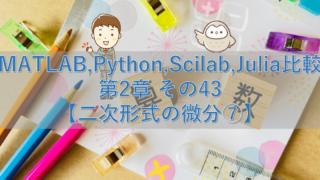 数値計算
数値計算