 AI、データサイエンス
AI、データサイエンス 第1次AIブーム(推論・探索の時代) その2 行動計画
前回に「推論・探索の時代」の続き。
行動計画、自動計画、プランニングという領域があるらしいので超簡単に調査&記載。
ロボットの行動計画も探索で実施可能。
特に古典プランニングの以下は「積み木の世界」を例とされることが多い。
 AI、データサイエンス
AI、データサイエンス  AI、データサイエンス
AI、データサイエンス  AI、データサイエンス
AI、データサイエンス 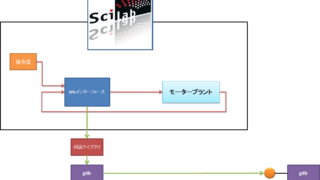 gdb
gdb 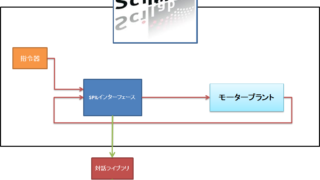 gdb
gdb 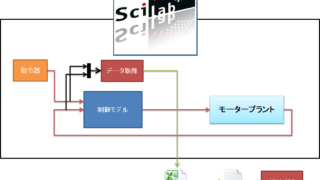 gdb
gdb 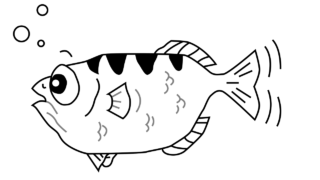 gdb
gdb 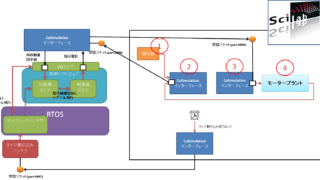 scilab
scilab 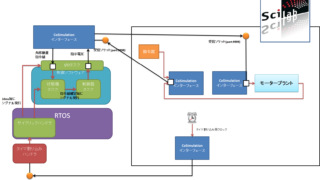 scilab
scilab 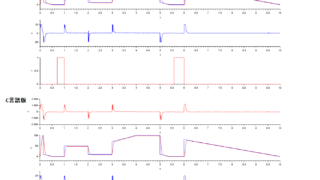 scilab
scilab